人に何かを伝えるという意味で使われる「言伝て(ことづて)」と「言付け(ことづけ)」ですが、これら2つの単語の違いを皆さんは考えたことがあるでしょうか?
語感が似ていることや記事内でも見ますが意味も似ているので、大きな違いはないように思うかもしれません。
今回の記事では「言伝て」と「言付け」について、関連した単語も含めて、読み取っていく記事になります。
5つに分けて見る「言伝て」と「言付け」
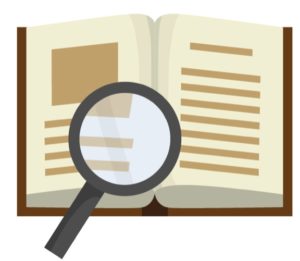
「言伝て」と「ことづて」
ことづて【言伝・言伝て】
- 人に頼んで伝言してもらうこと。また、その言葉。伝言。
- 間接的に人から伝え聞くこと。
ことづけ【言付け・託】
人に頼んで相手に伝えてもらうこと。また、その言葉。
この2つの読み方の場合だと、ほとんど同じ意味になっています。
しかし、「言伝て」と「ことづけ」ではその伝言に含まれる要素が異なります。
「言伝て」は書いてある字の通り、「言葉」を伝えるという意味ですが、「ことづけ」は言葉以外の「物」や「思い」について使うことができます。
これは「ことづけ」の「託」の字の方の意味合いになります。
「託す(たくす)」は「手紙を託す」や「希望を託す」といった「物」や「思い」に対しても使えるところから、別の字で同じ読みである「言付け」の方にも同じ意味合いが付いたのです。
例文としては、「荷物を言付け(託)られました」と言う事はできますが、「荷物を言伝られました」と言う事はできません。
つまり、「言付け・託>言伝て」の関係になっているということです。
「言伝え」と「いいつけ」
「言伝て」は送り仮名を変えると「言伝え(いいつたえ)」という言葉になり、「言付け」は別の読み方で「いいつけ」と読むことができます。
いいつたえ【言い伝え・言伝え】
- 昔方語り伝えられてきた話や習慣。
類義語:伝説、言い習わし - 伝言。ことづて。
いいつけ【言い付け・言付け】
人に、何かしろと言う命令。
類義語:指示、指図
「言伝え」の方は伝言としての意味もありますが、それより前に昔から伝えられたことに対して使う言葉になっています。
「言伝え」を使う文を考えると、「この村の言伝えを調べる」などの文を例に挙げることができます。
一方の「言付け」は、ただの伝言という意味ではなく、上から指示するような意味を持っています。
「言付け」を使う文を考えると、「親の言付けを守る」などの文を例に挙げることができます。
「言伝え」と「ことづけ」
「言伝え」と「言付け(ことづけ)」の2つで見ても、「言伝え」は伝えることは昔の人から伝えられた「言葉」ですので、伝言の意味としては同じように「言付け・託>言伝え」になっています。

「いいつけ」と「ことづけ」
「言付け」で2つの読み方ができますが、読み方で言葉の意味合いが少しだけ変わっています。
「ことづけ」の方は先ほども書いたように「託」としての意味が入っています。
敬語表現で物を頼む場合は、「言付け(ことづけ)」もしくは「託」の方を使うことになります(例:先方から言付けを預かっております)。
その事から「ことづけ」に関しては丁寧語で「おことづけ」とすることができます。
「いいつけ」の方は、美化語(上品に言い表そうとする言い方)としては「おいいつけ」も間違いとも言い切れないのですが、違和感があります。
「託」の字は「託宣」や「神託」のというものに使われるように「神が他のものの口を借りて言う」という意味もあります。
そこから丁寧語にできるところも「託」の意味合いが入っていることが考えられます。
「言伝え」と「言伝て」
この2つはほぼ同じ意味になっていますが、敬語表現で使う時には「(お)言伝」の方になります(例:言伝をお願いしてもよろしいでしょうか)。
「いいつたえ」を美化語と考えて「お言伝え」にした場合は、やはり違和感があります。
「言伝て」の方が丁寧語にできる理由としては、「託」のような別の読み方があるわけではないので、明確なことは何も言えません。
「言伝え」と「言伝」は両方とも古くから使われている言葉ですし、ほぼ同じ意味合いでこのような差が出るのは、語感の良さくらいしか考えられないと思います。
まとめ
今回は「言伝て」と「言付け(いいつけ・ことづけ)」について見ていきました。
同じような表記でも読み方が変わることで微妙に意味合いが変わるのが、日本語の難しいところであり、面白いところですね。
